特定技能介護人材の支援活動を通じて見える課題とは
― 現場の声に耳を傾けて ―
日本の介護業界において、外国人材の受け入れはもはや珍しいものではなくなりました。
特に「特定技能介護」制度の導入により、各地の介護施設で外国人スタッフが活躍する姿が日常の風景となっています。
私たちは登録支援機関として、そうした外国人介護士の受け入れ前から入国後、定着支援に至るまでの一連の活動をサポートしています。
その中で見えてくるのは、制度の枠組みでは想像しきれない、リアルな“課題”です。
日本語の壁は、試験では見えない
介護技能と日本語の試験に合格して来日した方々でも、現場で苦労することは少なくありません。
例えば…
- 方言や専門用語が多く、職員の指示が聞き取れない
- 利用者の“声にならないニーズ”を読み取るのが難しい
- 曖昧な日本語(例:「様子を見ておいて」)への対応に戸惑う
日本語のN4レベルでは、「理解する」「表現する」には限界があります。
このギャップは、本人にも職場にもストレスを生みかねません。
生活支援は“準備”だけでは足りない
私たちは入国後の住居確保や行政手続きなど、生活面の支援も行っていますが、生活は“用意すれば終わり”ではありません。
例えば…
- ゴミ出しのルールを知らずに近隣トラブルに
- 寂しさからホームシックや精神的な不調を訴える
- 日本人の生活リズムや食文化への戸惑い
こうした背景を理解し、継続的に“見守る支援”が不可欠です。
職場の「温度差」が生むすれ違い
受け入れ側の施設でも、良好な関係を築こうと努力されていることは多いです。
しかし現場では以下のような温度差が生まれることも。
- 丁寧に教えたつもりでも伝わっていなかった
- 遠慮して本音が言えないまま不満がたまる
- 期待と現実のギャップからモチベーションが低下
つまり、双方に「分かり合っているつもり」があることこそが、誤解の始まりになり得るのです。
支援とは、“育てる姿勢”と“寄り添う時間”
私たち支援機関ができることは、
「制度を使う」ことではなく、
「人を支え、関係を育てる」ことだと実感しています。
外国人介護士は、労働力ではなく、一人の生活者・仲間・成長する人材です。
支援を通じて信頼関係が生まれたとき、彼ら・彼女らは介護の現場に温かい変化をもたらしてくれます。
🔚 おわりに:制度の先にある“人と人との関係”を見つめて
特定技能介護の制度はまだ新しく、現場には改善の余地も多くあります。
けれど、ひとつ言えるのは、一人の人材との丁寧な関わりが、やがてチームと社会の在り方を変えていくということです。
「支援」とは、“特別なこと”ではなく、
“すぐそばにいる誰かに、少し心を配ること”なのかもしれません。
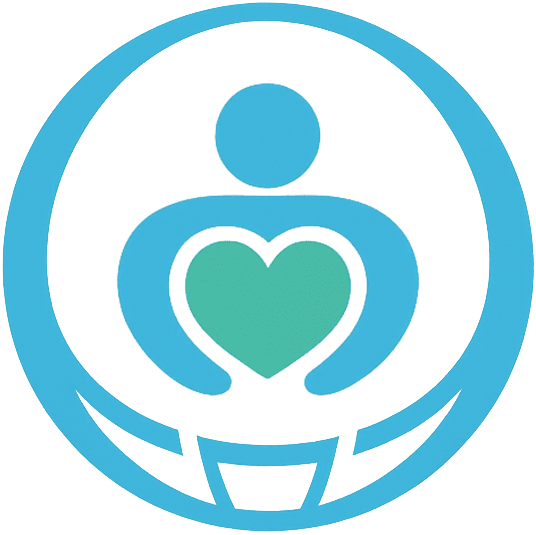 一般社団 外国人介護留学生支援機構
一般社団 外国人介護留学生支援機構