日本の介護現場は深刻な人材不足が進行しており、特に都市部での人手確保は急務となっています。「外国人介護人材 雇用条件」に対する正確な理解は、安心して外国人を受け入れるうえで不可欠です。当ページでは、特定技能「介護」や在留資格「介護」、EPAなど外国人介護人材の雇用に関わる制度を整理し、給与・労働時間・社会保険などの法令上の雇用条件や注意点をわかりやすく解説します。さらに、採用から入社後の支援までを包括的に支援する「登録支援機関」を利用することで、雇用主様がリスクや手間を抑え、安心して雇用プロセスを進められる流れもご紹介します。
1. 外国人介護人材における主な在留資格と雇用条件
特定技能「介護」
在留期間は通算 最長5年。1号の制度は2号が存在せず、5年を超えて継続雇用するには介護福祉士資格取得による在留資格「介護」への移行が必要です。
雇用形態は正社員のみで、賃金・労働条件は日本人と「同等以上」であることが法律上義務化されています。
対応業務は、身体介護(入浴・排泄等)と付随する支援業務であり、2025年4月以降、要件を満たせば訪問系サービスにも従事可能となりました。
夜勤業務も可能ですが、最初の約6か月は先輩職員と一緒に行い、安全確保の体制を整えることが求められます。
受け入れ可能な外国人人材の数は、「常勤日本人職員数まで」という上限があり、在留資格「介護」保持者や永住者も含めて人数制限が適用されます。
在留資格「介護」
国家試験に合格して介護福祉士の資格を取得済であることが前提。在留期間の制限はなく、家族帯同も可能です。
日本語能力(JLPT N2以上)や実務経験が求められ、採用者が即戦力として期待されます。
EPA介護福祉士候補者/技能実習「介護」
EPA制度は、母国で研修を受け4年間来日し、その後国家資格取得などにより在留資格へ移行する方式です。
技能実習制度は2023〜24年に廃止される予定ですが、在留中に特定技能への移行が可能です。ただし制度変更が進むため注意が必要です。
2. 雇用契約・待遇整備における注意点
- 労働条件・契約書の整備
- 生活支援・職場定着支援
- 採用までの期間と費用負担
3. 登録支援機関を活用する安心の流れ
● ステップ1:対象者選定と試験合格
● ステップ2:採用契約と支援計画の策定
● ステップ3:各種届出・在留資格申請
● ステップ4:入社後の生活支援と定着フォロー
4. 登録支援機関を利用するメリットまとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ✅ 法的コンプライアンス | 支援計画の策定や協議会加入など義務事項に対応 |
| ✅ 採用工数の削減 | 書類作成・在留申請・支援計画策定の負担を軽減 |
| ✅ 定着支援の一元管理 | 生活支援・日本語研修・相談対応などを支援機関が代行 |
| ✅ 離職リスクの抑制 | 採用ミスマッチの防止や職場適応支援による定着率向上 |
| ✅ 万一の対応サポート | 出入国管理庁や地方自治体との連携・行政対応支援を提供 |
5. 実際の導入までの流れ(例)
支援機関へ相談・ヒアリング
支援機関に委託契約の締結
人材マッチングと採用
在留申請と入国前対応
入職後の生活・日本語・相談支援
6. まとめ:雇用条件を理解し、登録支援機関を活用して安心雇用へ
外国人介護人材の雇用には、特定技能「介護」・在留資格「介護」・EPAなど、制度ごとに異なる取得要件や労働条件の整備が求められます。雇用契約、賃金、社会保険、夜勤体制などを法令に基づいて正確に設計することは、雇用主の大きな責務です。
特に「特定技能」制度では、入社前後を通じて10項目以上の生活・労務支援が義務付けられており、現場の通常業務と並行してこれをすべて対応するのは非常に困難です。
そこで重要になるのが、登録支援機関の活用です。支援機関に委託することで、採用業務の負担軽減はもちろん、法令遵守の支援、ミスマッチ防止、生活支援の一元管理が可能となり、施設様が本来注力すべき介護サービスの質の維持・向上に専念できる環境が整います。
貴社のように、実績と支援体制を備えた登録支援機関と連携することで、初めての外国人雇用でも安心してスタートを切ることができます。ぜひ今後の人材確保策として、登録支援機関を活用した外国人介護人材の計画的な導入をご検討ください。貴社の介護現場の安定運営とサービス品質向上を力強く後押しいたします。 ご相談・お問い合わせはこちら
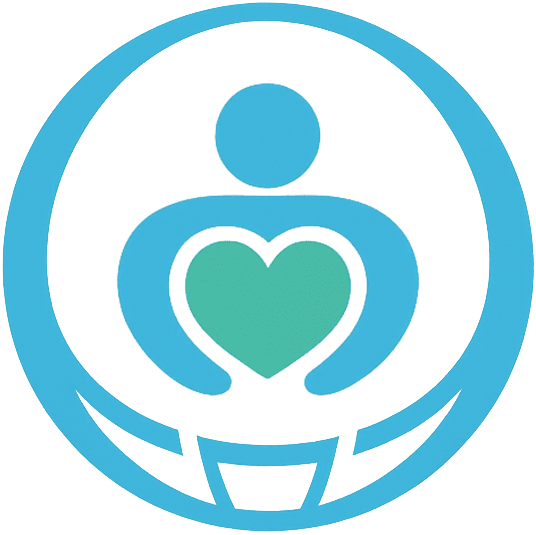 一般社団外国人介護留学生支援機構
一般社団外国人介護留学生支援機構