厳しい少子高齢化が進む日本において、介護現場の人材不足は深刻な社会問題となっています。2025年には約37万人の介護職員が不足すると予測され、中でも地方における介護サービスの維持が困難な状況です。こうした中、外国人介護人材の受け入れは、人手不足を補うだけでなく、職場に多様性と活力をもたらし、利用者に寄り添ったケアの実現にも貢献します。本ページでは、日本の介護労働人口と、外国人介護労働者数の最新データをもとに、受け入れの意義、制度、導入のメリット・留意点を詳しくご紹介し、貴社の外国人介護人材受け入れを成功に導くための情報を提供します。
日本全体の介護労働人口の現状
厚生労働省の「第8期介護保険事業計画」によれば、2025年度末には介護職員が約243万人必要とされる一方、2040年度末には約280万人に達するとされています。
その結果、2025年時点で約37万人〜38万人の介護職員が不足すると予測されており、これは全国の介護施設・在宅サービスに大きな影響を与える規模です。
さらに介護職の有効求人倍率は2024年時点で約3.84倍に達しており、求人4件に対して求職者1人という極度の売り手市場であることが浮き彫りになっています。
外国人介護人材の人数と構成
厚労省によると、医療・福祉分野における外国人労働者は約12万人で、外国人労働者全体の5.1%を占めています。その多くが介護現場で活躍しています。
また、特定技能介護の在留者数は2024年12月末時点で約4万4千人に達しており、制度開始以降、年々増加傾向にあります。
介護分野の外国人介護士を雇用している事業所は、調査によれば82.7%が過去に雇用経験があり、59.1%が現在も雇用中、さらに10.9%が若手確保目的で検討中と答えています。一方、業界全体では8割以上の事業所が「まだ受け入れていない」状況ですが、今後の受け入れ意向は増加傾向にあります。
なぜ外国人介護人材受け入れが必要か?
- 人手不足の即効対策:
日本人だけでは賄えない人材ギャップを埋める手段として、特定技能制度や技能実習制度(2027年からは育成就労制度へ移行)を通じて即戦力を確保。 - 専門性と定着性:
在留資格「介護」を持つ外国人は介護福祉士国家試験合格者で、更新制限なく実質無期限滞在可能のため、継続的な雇用と職場定着が期待できます。 - 多様性による職場強化:
異文化や異言語環境がもたらす視点の多様化は、サービス改善やチームワーク強化につながります。
受け入れにあたっての注意点
- 日本語能力
N4レベルから必要、意思疎通に不安
対応策: 日本語研修・OJTの実施 - 文化・習慣の違い
利用者の抵抗や勤務形態の混乱
対応策: 職員・家族への理解促進、文化交流活動 - 雇用制度・手続き
雇用契約、ビザ手続き、更新管理
対応策: 専門支援機関の活用、研修プログラム整備
当社が提供するサポート内容
- 外国人介護人材の採用支援:
技能実習生、EPA、特定技能外国人まで幅広くご紹介 - ビザ・在留資格手続きの代行:
日本語試験、介護技能評価試験、行政対応まで一括支援 - 定着支援・研修プログラム:
日本語・介護技術・職場文化研修による即戦力化支援 - 定期フォローと定着支援:
離職防止・定着率向上のための継続フォローアップ
外国人介護人材を受け入れることで得られる成果
- 即戦力人材の確保:
離職率が低い、経験者中心の採用が可能 - 介護サービスの質向上:
多文化的な視点の導入によるケア品質の向上 - 介護職のイメージ改善:
やりがい・社会貢献性の高い職場としてのPR効果
まとめ:今こそ、外国人介護人材受け入れを始めるべき理由
日本の介護業界は2025年に約37万人の不足を控えており、243万人の介護職員が必要という状況です。外国人介護労働者は約12万人、そのうち特定技能介護の在留者は約44,000人に達しており、今後も増加見込みがあります。82.7%の事業所が外国人介護士を雇用した経験を持ち、59.1%が継続雇用中という実績もあります。制度的には技能実習・特定技能・在留資格「介護」の各制度があり、長期的な戦力化が可能です。
お問い合わせはこちら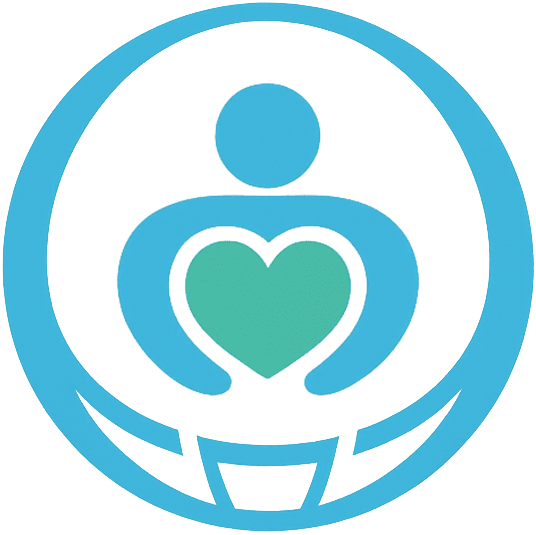 一般社団外国人介護留学生支援機構
一般社団外国人介護留学生支援機構