大阪の介護現場では、近年ますます多くの外国人介護人材が活躍しています。一方で、言葉や文化の違いによって、職員間のコミュニケーションに課題を感じるケースも少なくありません。こうした状況の中で、円滑なコミュニケーションを築き、外国人スタッフが安心して働き続けられる環境を整えることが、今後ますます重要になっています。
1. 多文化コミュニケーションの重要性
多文化コミュニケーションとは、異なる言語や価値観を持つ人々が、お互いを理解しながら協力して働くための取り組みを指します。介護の現場では、チームワークが不可欠であり、文化的背景を理解することが良好な職場環境をつくる第一歩です。
さらに、外国人スタッフが「理解されている」と感じることで、自信を持って業務に取り組めるようになり、結果として離職防止や定着率の向上にもつながります。
2. 導入初期における文化理解とサポートの工夫
外国人介護人材を受け入れる際は、まず「日本の介護文化」と「外国の生活習慣」の違いを共有することが重要です。例えば、日本では高齢者に対して敬語を使うことが自然ですが、他国ではフランクな言葉遣いが好まれる場合もあります。このような違いを事前に説明し、実際の場面で困らないようにすることで、ミスマッチを防ぐことができます。
一方で、外国人スタッフの母国文化にも理解を示すことが大切です。例えば、ベトナムでは人の頭を触る行為が失礼にあたるとされており、こうした宗教・文化的な背景に配慮することが信頼関係の構築に役立ちます。
3. 定着支援のための具体的な取り組み
大阪の介護施設では、外国人スタッフが長く働き続けられるよう、さまざまな支援が行われています。その中でも、日本語学習支援やメンター制度、多文化交流イベントの導入は効果的です。
例えば、勤務後に日本語を学ぶ時間を設けたり、職場内で日本語表現をサポートする先輩スタッフを配置することで、日々の業務に自信がつきます。さらに、外国人スタッフ同士だけでなく、日本人職員とも交流できる食事会や文化紹介イベントを開催することで、相互理解とチームの一体感が生まれます。
文化の違いに配慮することは、外国人だから特別というわけではありません。性別や年齢、価値観が異なる日本人同士の職場でも、同じように「思いやり」や「気遣い」が必要です。つまり、多文化コミュニケーションとは「外国人対応」ではなく、「多様な人が共に働くための基本姿勢」なのです。
そのため、施設全体で「違いを尊重する文化」を育てることが、外国人スタッフの定着にも直結します。
5. 現場の声 ― 大阪らしいあたたかさが生む信頼関係
大阪市内のある介護施設では、ベトナム人スタッフが入職して3年目を迎えました。入社当初は言葉に不安を感じていましたが、利用者との日々の会話の中で自然と日本語を覚えたそうです。スタッフは「最初は敬語が難しかったけれど、利用者さんが優しく教えてくれたおかげで楽しく学べた」と笑顔で話します。
一方、日本人スタッフも「文化が違うからこそ、新しい発見が多い。お互いに学び合える関係ができた」と語ります。人情の街・大阪らしく、日常のやり取りの中で自然に生まれる思いやりが、職場の空気をやわらかくしているのです。中には「大阪弁を教わって、今では利用者さんとの会話が楽しい」と話すスタッフもいます。
6. 今後の展望 ― 多文化共生の大阪モデルへ
大阪は全国でも外国人介護人材の受け入れが特に進む地域の一つです。今後は、介護現場の多様性を生かし、外国人スタッフと地域住民、利用者が一体となって支え合う「多文化共生型の介護モデル」の構築が期待されています。
そのためには、行政・教育機関・福祉法人が連携し、日本語教育支援や生活サポート、キャリア形成支援を一体的に進めることが欠かせません。加えて、現場レベルでの「学び続ける文化」を根づかせることで、介護職全体の専門性も高まります。
大阪の介護現場が、国籍や文化の違いを超えて支え合う「共生のモデル都市」となる日も、そう遠くはないでしょう。
7. まとめ ― 共に支え合う職場づくりを目指して
大阪の介護現場では、外国人介護人材が欠かせない存在になっています。しかし、真の意味で共に働くためには、制度やマニュアル以上に人と人との理解と信頼が求められます。
文化や言葉の壁を越えて助け合う姿勢を持つことで、介護の現場はもっと温かく、強くなる。そして、その一歩を踏み出すのは、日々の小さな「気づき」と「声かけ」からです。
青山信明は、これからも現場の声に耳を傾け、多文化共生の現場づくりを支援していきます。
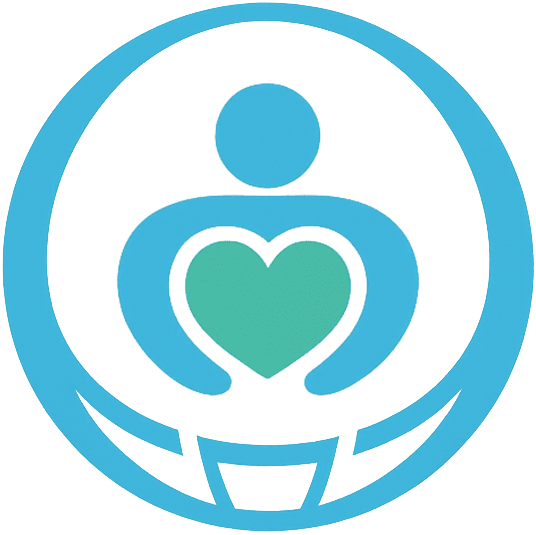 一般社団外国人介護留学生支援機構
一般社団外国人介護留学生支援機構 