インドネシア介護人材と日本の介護現場 ― 他国人材との比較でみる可能性
日本は世界でも類を見ないスピードで高齢化が進み、介護人材不足が深刻化しています。厚生労働省の推計によれば、2025年には全国で20万人以上の介護人材が不足する見込みです。その解決策として、東南アジア諸国からの介護人材受け入れが年々増加しており、特にベトナム・インドネシア・フィリピン・ミャンマーといった国々の人材が活躍しています。2023年末時点で、特定技能介護で働く外国人はベトナム人7,937人、インドネシア人7,411人、フィリピン人3,497人に達しました。関西圏の大都市である大阪でもこうした外国人介護人材の導入が進みつつあり、地域社会の支え手として重要な役割を果たしています。本記事では、インドネシア人介護人材の特徴を中心に、他国との比較を交えながら、日本の介護現場における可能性を解説します。
1. 日本の介護人材不足の現状
- 高齢者人口の増加に伴い、全国的に介護職員が不足。
- 厚労省の予測では2025年に20万人超の人材不足。
- 特に都市部や関西圏など需要が集中する地域では、採用競争が激しくなっている。
この背景から、外国人介護人材の受け入れは「特定技能」「技能実習」「EPA」などを通じて急速に広がっています。
2. インドネシア人介護人材の特徴
多くがイスラム教徒であり、食事や礼拝への配慮が必要。ただし協調性が高く、チームワークを重んじる姿勢が現場で評価されている。
日本語教育の充実インドネシアでは来日前研修で日本語教育が徹底され、N3レベルを目指す人材も多い。
受け入れ事例企業や福祉法人がインドネシア人材を採用するケースが増え、関西圏の施設でも活躍が広がっている。
3. 国別にみる介護人材の比較
外国人介護人材は国ごとに特徴があり、それぞれに強みと課題があります。採用を検討する際には、こうした国ごとの傾向を理解することが重要です。以下の表は、主要な送り出し国であるインドネシア・ベトナム・ミャンマー・フィリピンの特徴と採用メリットを整理したものです。
国名 特定技能介護 在留者数 特徴 採用メリット・課題
| 国名 | 特定技能介護 在留者数 | 特徴 | 採用メリット・課題 |
|---|---|---|---|
| インドネシア | 7,411人 | 温厚で協調性が高い。イスラム教徒が多く、食文化や宗教対応が必要。日本語教育制度が整備されつつある。 | 定着率が高い。介護の適性があり、真面目な人材が多い。文化面での理解支援が必要。 |
| ベトナム | 7,937人 | 日本語学習熱心でEPA受験者数も最多。若年層が多く学習意欲が高い。 | 勤勉で吸収力が高いが、都市部では人材獲得競争が激しい。帰国後のキャリアを重視。 |
| ミャンマー | 推計数千人規模 | 温厚で人当たりが良い。仏教徒が多く、日本文化に馴染みやすい。 | 日本語教育インフラが整備途上。採用コストは低めだが、研修体制が重要。 |
| フィリピン | 3,497人 | 英語力が高く、医療・看護教育の基盤あり。明るく社交的。 | 日本語習得に時間がかかる場合あり。EPA介護福祉士合格率が高い。 |
👉 この数字からも、ベトナムとインドネシアが介護人材の主要国であることが分かります。
また、特定技能全体(介護以外も含む)でみると、
- ベトナム:約110,648人
- インドネシア:約34,255人
- フィリピン:約21,367人
と、やはりベトナムとインドネシアが突出しています。
4. 外国人介護人材を受け入れるメリット(具体例)
慢性的な人材不足の解消
特に夜勤や早朝シフトなど、日本人が敬遠しやすい時間帯に柔軟に対応できる人材が多い。
採用難が続く訪問介護やグループホームなど小規模施設でも、安定した勤務を希望するケースが多く、人材確保につながりやすい。
例:大阪市内の特養では、インドネシア人材を導入することで、欠員によるサービス縮小を回避し、安定した入居者受け入れが可能になった事例もある。
利用者へのプラス効果
明るく前向きな性格の人材が多く、利用者とのコミュニケーションで好印象を与える。
日本語が拙くても、笑顔や身振り手振りで丁寧に対応する姿勢が「安心感につながる」と高齢者から評価されることも多い。
利用者の家族からも「外国人スタッフがいると雰囲気が明るい」「多様性に富んだ職場で安心できる」という声が聞かれる。
職場全体の活性化
外国人材の前向きな姿勢に刺激を受け、日本人スタッフのモチベーション向上につながる。
異文化理解や多国籍のコミュニケーションを通じて、職場が風通しの良い雰囲気に変化する。
特に若い人材が多いため、現場に活気が生まれやすい。
長期的な定着の可能性
インドネシアやベトナムの人材は「介護福祉士資格取得」を目指すケースが多く、数年単位で働き続ける意欲がある。
介護福祉士に合格すると在留資格が安定し、長期雇用につながるため、事業所側にとっても教育コストが無駄になりにくい。
実際に特定技能から介護福祉士資格を取得し、正社員として活躍する外国人スタッフの事例は全国的に増えている。
助成金・制度の活用でコスト削減
厚労省の「外国人労働者就労環境整備助成コース」を活用すれば、日本語研修やマニュアル翻訳、生活支援の仕組みづくりに補助金を活用可能。
大阪府など自治体レベルでも、外国人材受け入れのための研修・支援プログラムが実施されており、導入初期の負担を軽減できる。
5. 採用と定着のために必要なこと
外国人介護人材を採用する際には、単に「雇用する」だけでは十分ではありません。文化や言語の壁を超えて、安心して長く働ける環境を整えることが重要です。以下のポイントを意識することで、定着率を高め、双方にとって良い雇用関係を築くことができます。
① 日本語学習の継続支援
介護現場では利用者や職員との円滑なコミュニケーションが欠かせません。日本語力が不十分なまま就労すると、誤解やストレスにつながる可能性があります。
来日前:送り出し機関と連携し、日常会話レベルに加えて介護用語を中心に学習できる環境を整える。
来日直後:入社研修と並行して日本語学習の時間を設ける。教材やeラーニングを活用することで学習を継続しやすくする。
就労後:資格取得(介護福祉士)を目標に、日本語能力試験(JLPT)対策講座や社内勉強会を実施。
👉 このように「段階的な学習支援」を行うことで、本人の自信が高まり、利用者や職員との信頼関係も深まります。
② 生活面の配慮
外国人材が安心して働くには、職場だけでなく生活環境の整備が不可欠です。
住環境のサポート:寮や社宅を用意し、生活用品の手配を支援。生活に関する相談窓口を設けると安心感が高まる。
宗教・食文化への配慮:インドネシア人材の場合、ハラル食対応や礼拝の時間確保が重要。食堂メニューの工夫や礼拝スペースの設置は、職員満足度向上につながる。
地域社会との交流支援:地域のイベントや日本人家庭との交流機会をつくることで、孤立を防ぎ、生活の安定を促進できる。
👉 職場外のサポートが整うことで「ここで働き続けたい」という気持ちにつながりやすくなります。
③ キャリア設計の明確化
「ただの労働力」として扱うのではなく、将来のキャリアパスを示すことが長期定着のカギになります。
資格取得の支援:介護福祉士資格を取得すると在留資格が安定し、本人のモチベーションも高まる。試験対策講座や模擬試験を事業所内で実施する取り組みも効果的。
キャリアアップの道筋:入職から数年後のキャリアを示し、「将来はチームリーダーや教育担当になれる」といった展望を持たせる。
正社員登用制度:契約社員や派遣社員から正社員へと登用する仕組みを整えることで、本人の安心感と定着意欲が向上する。
👉 外国人材自身が「自分はここで成長できる」と感じられることが、長く働き続けてもらうための最大のポイントです。
④ 職場環境の改善と周囲の理解
外国人材が働きやすい環境をつくるには、本人だけでなく周囲のスタッフの理解も必要です。
異文化理解研修:既存の日本人スタッフに対し、宗教・文化・言語の違いを学ぶ機会を提供する。
多言語マニュアルの整備:業務手順や介護記録を英語や母国語で補足することで、初期段階の不安を軽減。
相談体制の確立:困りごとを気軽に相談できるメンターや担当者を配置。
👉 職場全体で受け入れる体制が整えば、外国人材の孤立を防ぎ、自然に職場に溶け込めます。
まとめ
外国人介護人材の採用は「雇用契約を結ぶ」ことがゴールではなく、そこからが本当のスタートです。日本語学習の継続支援、生活面でのサポート、将来を見据えたキャリア設計、そして職場環境の改善といった多角的な取り組みを組み合わせることで、安心して長く働ける環境が整い、人材の定着や事業所の安定経営につながります。
私たちは大阪を拠点に活動する登録支援機関として、こうした受け入れから定着までの一連の流れをワンストップでサポートしています。インドネシアをはじめ、ベトナム・ミャンマー・フィリピンなど各国の介護人材の採用を円滑に進めるために、在留資格手続き・生活支援・日本語教育・キャリア形成支援まで包括的に対応可能です。
「人材不足を解消したい」「外国人スタッフを安心して迎え入れたい」とお考えの大阪や関西圏の介護事業者様に向けて、実務経験豊富な私たちが伴走し、最適な仕組みづくりをお手伝いいたします。外国人介護人材の採用・定着をご検討中の方は、ぜひ一度ご相談ください。
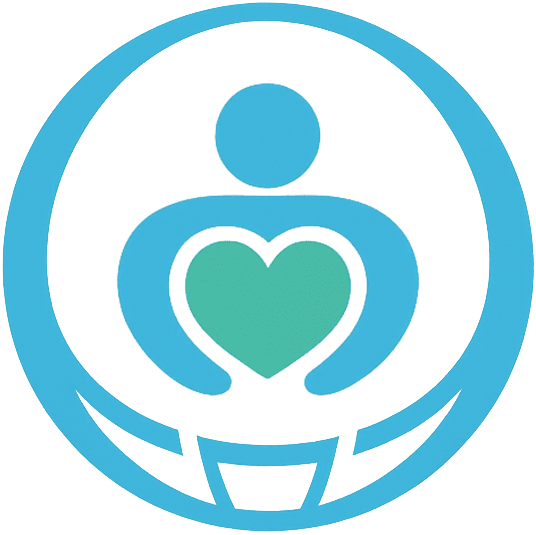 一般社団外国人介護留学生支援機構
一般社団外国人介護留学生支援機構